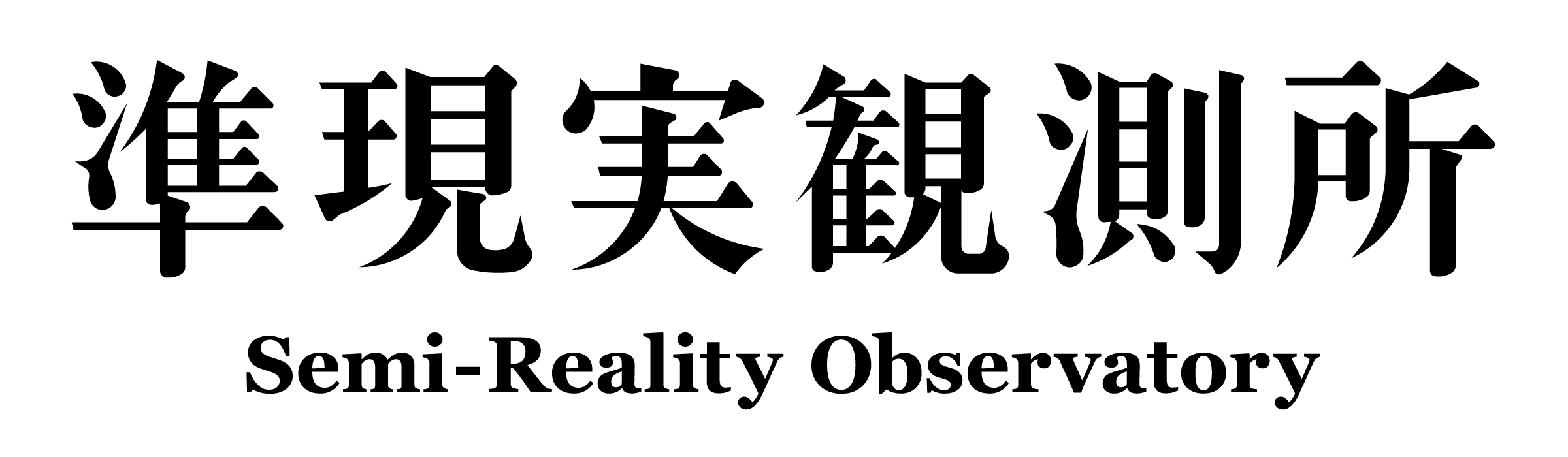“準現実”としての写真
写真は、「現実であったはずのもの」が、撮影の瞬間を経た時点で同一の実体としてはもはや存在しないという性格をもつ。ゆえに現実と“準現実”のあいだを媒介するメディアとして機能し得る。
私は、“準現実”を、静的で無表情な街角の光景を通じて観測している。




「ノスタルジア」と似て非なるもの
私が撮影する対象は、主に昭和後期の建築群である。しかし、それらはノスタルジアの対象ではない。これらの被写体は、近年急速に社会的機能を失いつつあるという点で「現実と喪失の境界」に位置しており、その構造が“準現実”のありようと同期する。


“準現実”的な画面とは何か
“準現実”の視覚性とは何かを考えるとき、まずはその「静的(static)な構造である」という特徴が重要となる。これを物質的に翻訳すると「硬直した構造物」としての姿をしているということになり、直線に構成された建築的な視覚要素として現れる。「主体なき制御」が行われているかのように偶発的に硬直しているのである。
加えて、平たく言えば「ノイズとなる現実感の強い要素を排除する」という消極的な選択も不可欠となる。直接的な記号性(人間や動物、過剰なドラマ性やレトロ感、撮影者の視点を主張する技法など)を抑制し、なるべく無人称性・無事件性を保つ。なお、その上でも少量の営為の痕跡が残るわけであるが、これは“準現実”が虚構へと転落しないための最後のアンカーとして働く。